野生のハクビシンは夜行性?【活動時間の95%が夜間】昼間の対策だけでは不十分、24時間の備えが被害防止のカギ

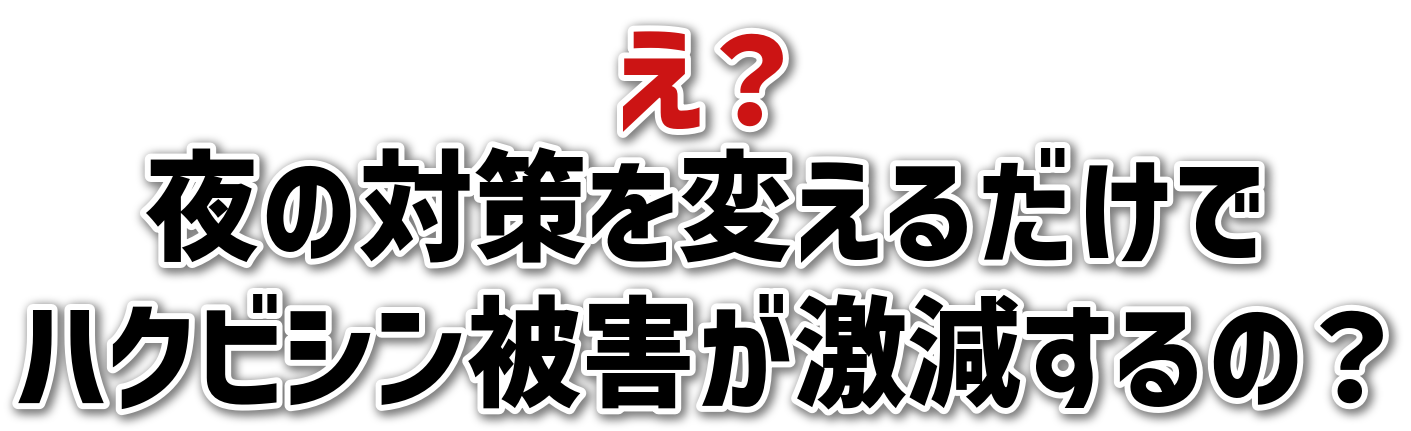
【この記事に書かれてあること】
夜中に「ガサガサ」という音。- ハクビシンの活動時間の95%以上が夜間に集中
- 日没後2時間がハクビシン出没のピーク時間
- 昼間は樹洞や茂みで休息する習性
- ハクビシンの行動圏は1~2平方キロメートル
- 夜行性を利用した効果的な対策方法で被害を軽減
屋根裏から聞こえてくる爪の音。
庭の果物が食べられた跡…。
これらはハクビシンの仕業かもしれません。
実は、野生のハクビシンは典型的な夜行性動物なんです。
その活動時間の95%以上が夜間に集中しているんです。
「え?そんなに夜型なの?」と驚かれるかもしれません。
でも、この習性を理解することで、効果的な対策が可能になります。
ハクビシンの夜の世界をのぞいてみましょう。
その生態を知れば、被害を大幅に減らせるかもしれません。
【もくじ】
野生のハクビシンの夜行性と活動パターン

ハクビシンの活動時間の95%は「夜間」に集中!
ハクビシンは、活動時間のほとんどを夜に費やす典型的な夜行性動物です。なんと、その活動時間の95%以上が夜間に集中しているんです。
「えっ、そんなに夜型なの?」と驚かれるかもしれません。
でも、ハクビシンにとって夜こそが活動のゴールデンタイムなんです。
昼間はぐっすり寝て、夜になると元気いっぱいに動き回ります。
ハクビシンの1日の活動時間は平均して6時間程度。
その大部分が日没後から夜明け前までの真っ暗な時間帯に集中しています。
まるで「夜の忍者」のように、静かに、でも活発に活動するんです。
では、なぜハクビシンはこんなにも夜行性なのでしょうか?
その理由は主に3つあります:
- 捕食者から身を守るため
- 餌を見つけやすいため
- 人間との接触を避けるため
昼間に活動する捕食者の目を避けながら、自由に動き回れるんです。
また、果物や昆虫などの好物も、夜間に活動することが多いため、餌探しにも都合が良いのです。
さらに、夜行性であることで人間との接触も最小限に抑えられます。
「人間が寝ている間に活動すれば、邪魔されずに済む」というわけです。
このようなハクビシンの夜行性を理解することは、効果的な対策を立てる上で非常に重要です。
夜間に重点を置いた対策を行うことで、ハクビシンによる被害を大幅に減らすことができるのです。
日没後2時間が最も活発!「ハクビシン出没のピーク時間」
ハクビシンの活動時間の中でも、特に注目すべきは日没後2時間です。この時間帯がハクビシン出没のピーク時間なんです。
「日が暮れたらすぐに活動開始!」というわけではありません。
ハクビシンは慎重な性格で、完全に暗くなってから行動を始めます。
そして、日没から約2時間後、辺りが真っ暗になった頃に最も活発になるのです。
具体的には、季節によって多少の違いはありますが、だいたい次のような時間帯がピークになります:
- 夏:午後8時?10時頃
- 春・秋:午後7時?9時頃
- 冬:午後6時?8時頃
「今日も美味しいものを見つけるぞ!」とばかりに、果敢に行動を開始します。
庭の果樹や家庭菜園、ゴミ置き場などを目指して、てくてくと歩き回るのです。
ハクビシンの視力は人間ほど優れていませんが、その分、嗅覚と聴覚が非常に発達しています。
真っ暗な中でも、鼻と耳を頼りに餌を探し当てる能力は驚くほどです。
「キュルキュル」という独特の鳴き声も、この時間帯によく聞こえます。
仲間同士でコミュニケーションを取りながら、効率よく餌を探しているんですね。
このピーク時間を知っておくことで、ハクビシン対策の効果を大幅に高めることができます。
例えば、この時間帯に合わせて自動点灯するセンサーライトを設置したり、ゴミ出しの時間を調整したりすることで、被害を未然に防ぐことができるのです。
昼間は樹洞や茂みで休息!「ハクビシンの隠れ家」を知ろう
ハクビシンは夜行性ですから、当然昼間は休息をとります。でも、その休息場所がどこなのか、ご存知ですか?
実は、ハクビシンの隠れ家を知ることも、効果的な対策を立てる上で重要なポイントなんです。
ハクビシンが昼間に好んで休む場所は、主に次の3つです:
- 樹洞(古い木の幹の中にできた穴)
- 茂みの中
- 岩場の隙間
なぜなら、これらの場所は外敵から身を隠すのに最適で、なおかつ暑さや寒さをしのぐのにも適しているからです。
特に樹洞は、ハクビシンのお気に入りです。
「まるで自分専用のベッドルーム!」とでも言いたげに、すやすやと眠っています。
樹洞は上から覆われているので雨風をしのげますし、中は意外と広いので、体を丸めてぐっすり休めるんです。
茂みの中も人気の休息場所です。
葉っぱが密集している場所を選び、その中に潜り込みます。
外からは見えにくいので、安心して眠れるというわけです。
岩場の隙間も、ハクビシンにとっては格好の隠れ家です。
狭い隙間に体を押し込むことで、外敵から身を守ります。
「ここなら誰にも見つからないぞ」と、安心して休んでいるのでしょう。
ただし、注意が必要なのは、人家の近くでは建物の隙間や屋根裏、物置なども隠れ家として利用することです。
これらの場所は、自然の隠れ家と同じように安全で快適だとハクビシンは考えているのです。
ハクビシンの隠れ家を知ることで、対策の幅が広がります。
例えば、庭木の手入れを定期的に行い、ハクビシンが隠れそうな場所を減らすことができます。
また、建物の隙間をふさぐことで、家屋への侵入を防ぐこともできるのです。
夜行性がもたらす「人間との接触機会」に要注意!
ハクビシンの夜行性は、人間との接触にどのような影響を与えるのでしょうか?実は、この夜行性という特徴が、思わぬところで人間生活と衝突を引き起こしているんです。
まず、最も大きな影響は家屋侵入や農作物被害です。
ハクビシンが活動を始める夜間は、ちょうど人間が活動を終える時間。
「人間が寝ている間に、こっそり行動しよう」とばかりに、ハクビシンは家屋に侵入したり、畑を荒らしたりするのです。
具体的には、次のような被害が報告されています:
- 屋根裏や壁の中への侵入
- 果樹園や家庭菜園の農作物の食害
- ゴミ置き場の荒らし
- ペットフードの盗食
「朝起きたら、畑のトマトが全部なくなっていた!」なんていう悲鳴も、よく聞かれるんです。
また、夜行性であるがゆえに、ハクビシンとの直接的な遭遇は比較的稀です。
でも、だからこそ注意が必要なんです。
夜間の外出時や早朝・夕暮れ時には、思わぬところでハクビシンと鉢合わせする可能性があります。
「キャー!何か動いた!」なんて驚いて、転んでケガをしてしまうこともあるんです。
特に、ゴミ出しの時間がハクビシンの活動時間と重なる場合は要注意です。
ただし、ハクビシンは基本的に臆病な動物です。
人間を見ると、すぐに逃げ出そうとします。
でも、逃げ場を失うと攻撃的になることもあるので、むやみに近づくのは危険です。
夜行性のハクビシンと上手く付き合うには、その習性を理解し、適切な対策を講じることが大切です。
例えば、夜間のゴミ出しを控えたり、庭にセンサーライトを設置したりすることで、ハクビシンとの不要な接触を避けることができるのです。
ハクビシンの行動圏は「1~2平方キロメートル」に及ぶ!
ハクビシンの行動圏、つまり日常的に活動する範囲がどれくらいか、ご存知ですか?なんと、1匹のハクビシンの行動圏は、平均して1~2平方キロメートルにも及ぶんです。
これは東京ドーム約20?40個分の広さに相当します。
「えっ、そんなに広いの?」と驚かれるかもしれません。
でも、この広い行動圏は、ハクビシンの生存戦略にとって重要な意味があるんです。
ハクビシンがこれほど広い範囲を動き回る理由は、主に次の3つです:
- 十分な食糧を確保するため
- 安全な休息場所を確保するため
- 繁殖のためのパートナーを見つけるため
でも、これらの食べ物は季節や場所によって偏在しています。
そのため、広い範囲を移動しながら、その時々で最適な食べ物を探す必要があるんです。
また、安全に休息できる場所も、あちこちに確保しておく必要があります。
「今日はあっちの樹洞で寝よう、明日はこっちの茂みで休もう」なんて具合に、休息場所を変えながら生活しているんです。
さらに、繁殖期には異性を求めて広く移動します。
「素敵なパートナーはどこかな?」と、広い範囲をくまなく探し回るわけです。
この広い行動圏を考えると、ハクビシン対策は一軒の家だけでなく、地域全体で取り組むことが重要だと分かります。
例えば:
- 近所で協力して、ゴミの管理を徹底する
- 地域ぐるみで、果樹の収穫を適切に行う
- 空き家の管理を適切に行い、ハクビシンの侵入を防ぐ
「ハクビシンの行動圏は広い」という事実を知ることで、対策の視野も広がります。
一軒だけでなく、ご近所さんと協力して対策を講じることで、より効果的にハクビシン問題に対処できるのです。
ハクビシンvsタヌキ・アライグマ 夜行性動物の特徴比較
ハクビシンとタヌキ「夜行性の度合い」はどちらが強い?
ハクビシンの方が、タヌキよりも夜行性の度合いが強いんです。驚きですよね。
ハクビシンは、その活動時間の95%以上を夜間に集中させる超夜型生活者。
まるで、夜のパーティーに招待された常連さんのようです。
「夜が来た!さあ、活動開始だ!」とばかりに、日没とともに元気いっぱいになるんです。
一方、タヌキはどうでしょうか。
タヌキも夜行性ですが、ハクビシンほど極端ではありません。
タヌキは薄明薄暮型と呼ばれる生活パターンを持っています。
これは、夕方から夜明けにかけて活動するスタイルのこと。
具体的には、タヌキの活動時間は次のようになっています:
- 夕方:活動開始
- 夜間:活発に行動
- 早朝:活動が続く
- 昼間:主に休息
「夜だけじゃなく、朝方までパーティーを楽しむぞ!」という感じでしょうか。
この違いは、両者の生態や進化の過程で生まれたものです。
ハクビシンは完全な夜行性に適応し、暗闇での活動に特化しています。
一方タヌキは、より柔軟な活動時間を持つことで、多様な環境に適応してきたんです。
この特性の違いは、対策を考える上でも重要なポイントになります。
ハクビシン対策は夜間に集中させる必要がありますが、タヌキ対策は夕方から朝方まで、より広い時間帯を考慮する必要があるんです。
「じゃあ、タヌキの方が対策が大変じゃない?」と思われるかもしれません。
でも、ハクビシンの夜行性が極端なだけに、その行動はより予測しやすいんです。
タヌキよりもハクビシンの方が、時間を絞った効果的な対策が立てやすい、というわけです。
ハクビシンvsアライグマ「夜間の行動パターン」の違い
ハクビシンとアライグマ、どちらも夜行性の動物ですが、その行動パターンには面白い違いがあるんです。まるで、夜の街を楽しむ二人の友達のように、それぞれ好みの遊び方が違うんです。
まず、ハクビシンの特徴から見てみましょう。
ハクビシンは木登りの達人。
高い所が大好きで、夜間の行動も高所中心になります。
例えば:
- 屋根の上を歩き回る
- 木から木へと飛び移る
- 高い場所から周囲を観察する
「今夜も屋根の上からいい景色だな〜」なんて言いながら、家々の上を歩き回っているかもしれません。
一方、アライグマはどうでしょうか。
アライグマは水辺での活動が多いのが特徴です。
その行動パターンは:
- 川や池の周りを歩き回る
- 水中に手を入れて餌を探す
- 水辺の生き物を捕まえて食べる
「今夜はどんな魚が捕れるかな?」とワクワクしながら、水辺を探索しているんです。
この行動パターンの違いは、両者の体の特徴にも表れています。
ハクビシンは細長い体と鋭い爪を持ち、木登りに適した体つき。
一方アライグマは、器用な前足と敏感な触覚を持ち、水中の餌を探すのに適しています。
でも、注意が必要なのは、どちらも適応力が高いこと。
環境によっては、ハクビシンが地上で活動したり、アライグマが木に登ったりすることもあるんです。
この違いを知ることで、効果的な対策が立てられます。
例えば:
- ハクビシン対策:屋根や高所への侵入防止に重点を置く
- アライグマ対策:水辺や地上レベルでの対策を重視する
「ふむふむ、屋根の上を歩く音がするな。これはハクビシンかもしれない!」なんて、detective気分で観察してみるのも面白いかもしれませんね。
ハクビシンとフクロウ「夜間の視力」はどちらが優れている?
夜の暗闇で視力を競うなら、フクロウの圧勝です。ハクビシンよりもフクロウの方が、はるかに優れた夜間視力を持っているんです。
フクロウの目は、まるで最新の夜間撮影カメラのよう。
その特徴は:
- 大きな眼球:体に対して非常に大きな目を持つ
- 光を集める能力:網膜に光を集める細胞が多い
- 動体視力:わずかな動きも見逃さない
「真っ暗な森の中でも、小さなネズミの動きが手に取るように分かるんだ」と、フクロウは自慢するかもしれません。
一方、ハクビシンの夜間視力はどうでしょうか。
実は、ハクビシンの目はそれほど発達していません。
でも、だからといって夜の活動に支障があるわけではないんです。
ハクビシンは、視力の代わりに嗅覚と聴覚を駆使して夜の世界を把握します。
その特徴は:
- 鋭い嗅覚:餌や危険を嗅ぎ分ける
- 優れた聴覚:微かな音も聞き逃さない
- 長い髭:周囲の状況を感知する
「目が見えなくても大丈夫。鼻と耳で周りの様子が手に取るように分かるんだ」と、ハクビシンは胸を張るでしょう。
この違いは、両者の生態や進化の過程で生まれたものです。
フクロウは空中から獲物を狩るため、優れた視力が必要でした。
一方ハクビシンは、地上や木の上で活動するため、嗅覚や聴覚の方が重要だったんです。
この特性の違いは、対策を考える上でも重要なポイントになります。
例えば:
- フクロウ対策:視覚的な威嚇(光など)が効果的
- ハクビシン対策:匂いや音を使った対策が有効
強い香りのハーブを植えたり、不規則な音を出す装置を設置したりするのが効果的かもしれません。
ハクビシンの「鼻と耳」を上手く利用した対策で、被害を減らすことができるんです。
ハクビシンの「嗅覚と聴覚」に注目!他の夜行性動物との比較
ハクビシンの嗅覚と聴覚は、夜の世界での生存に欠かせない武器なんです。でも、他の夜行性動物と比べるとどうなのでしょうか?
面白い違いがあるんですよ。
まず、ハクビシンの嗅覚は非常に発達しています。
その特徴は:
- 餌の匂いを遠くから感知できる
- 他の個体の存在を匂いで判断する
- 危険な状況も匂いで察知する
「今日の晩ご飯は果物かな?それとも小動物かな?」なんて、鼻を動かしながら考えているかもしれません。
聴覚も負けていません。
ハクビシンの耳は:
- 微かな物音も聞き逃さない
- 高い周波数の音まで聞こえる
- 音の方向を正確に判断できる
「あっち方向で何か動いたぞ。獲物かな?それとも天敵かな?」と、耳をピンと立てて注意を払っているんです。
では、他の夜行性動物と比べるとどうでしょうか?
コウモリと比べると、聴覚の面では一歩譲ります。
コウモリは超音波を使って エコーロケーションを行うため、聴覚の面では比べものになりません。
でも、嗅覚ではハクビシンの方が優れています。
ネコと比べると、聴覚はほぼ互角。
でも、嗅覚ではハクビシンの方が上です。
ネコは視覚に頼る部分が大きいのに対し、ハクビシンは嗅覚をより重視しているんです。
フクロウと比べると、両方の面でハクビシンの方が優れています。
フクロウは視覚に特化しているため、嗅覚と聴覚はそれほど発達していないんです。
この特性を理解すると、効果的な対策が立てられます。
例えば:
- 強い匂いのするハーブを植える
- 高周波音を出す装置を設置する
- 餌となる物の匂いを徹底的に管理する
ハクビシンの得意な感覚を逆手に取ることで、被害を大幅に減らすことができるんです。
匂いと音の世界で暮らすハクビシン。
その特徴を知ることで、私たちの対策も一歩先を行くことができるんです。
夜行性を理解して実践!効果的なハクビシン対策法

夜間限定の「自動散水装置」でハクビシンを撃退!
ハクビシンを追い払う意外な方法として、夜間限定の自動散水装置が効果的です。水を嫌うハクビシンの習性を利用した、ちょっと変わった対策法なんです。
「えっ、水でハクビシンが追い払えるの?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果があるんです。
ハクビシンは毛づくろいが大好きな清潔好きな動物。
突然の水しぶきは大の苦手なんです。
自動散水装置の設置場所は、ハクビシンの侵入経路を狙うのがポイント。
例えば:
- 庭の入り口付近
- フェンスや塀の周辺
- 家の壁際や軒下
使い方は簡単。
タイマーを付けて、ハクビシンが活動を始める夕方から夜明け前までの時間帯に作動するよう設定します。
「シュー!」という突然の水音と水しぶきに、ハクビシンはびっくりして逃げ出すんです。
この方法の良いところは、化学物質を使わないので環境にも優しいこと。
また、植物への水やりも兼ねられるので一石二鳥です。
「庭の植物も喜んでるかも」なんて想像すると、なんだか楽しくなりますよね。
ただし、注意点もあります。
冬場は凍結の危険があるので、寒冷地では使用を控えましょう。
また、近所迷惑にならないよう、水の飛び散る範囲にも気を付ける必要があります。
この方法を試してみると、「えっ、こんな簡単なことでハクビシンが来なくなるの?」と驚くかもしれません。
でも、実際に効果を実感している人も多いんです。
ハクビシンの夜行性を理解し、その習性を逆手に取った対策。
それが自動散水装置なんです。
人間の声を録音!「ラジオ作戦」で警戒心を誘発
ハクビシン対策の意外な切り札、それが「ラジオ作戦」です。人間の声を録音したラジオを夜間に低音量で流すことで、ハクビシンを警戒させる方法なんです。
「えっ、そんな簡単なことでハクビシンが寄ってこなくなるの?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
ハクビシンは警戒心が強く、人間の気配を感じると近づかない習性があります。
ラジオ作戦のポイントは、以下の3つです:
- 人間の会話が中心の番組を選ぶ
- 音量は小さめに設定する
- 時間帯は日没から夜明けまで
「ガヤガヤ」とした人間の声が、ハクビシンには「あ、人間がいる!危険だ!」と感じさせるんです。
音量設定も重要です。
大音量だと近所迷惑になりますし、ハクビシンが慣れてしまう可能性もあります。
小さな音でも、ハクビシンの鋭い聴覚なら十分に聞こえるんです。
設置場所は、ハクビシンの侵入経路や被害が多い場所を中心に選びましょう。
例えば:
- 庭の入り口付近
- 果樹の近く
- 家屋の周辺
家にあるラジオやスマートフォンで十分です。
また、電気代もそれほどかからないので、経済的な対策方法と言えます。
ただし、毎晩同じ場所で同じように流していると、ハクビシンが慣れてしまう可能性があります。
「あれ?ハクビシンが戻ってきちゃった」なんてことにならないよう、定期的に場所や番組を変えるのがコツです。
この「ラジオ作戦」、試してみると案外効果があって驚くかもしれません。
ハクビシンの警戒心を利用した、賢い対策方法なんです。
「おしゃべりが苦手なハクビシンさん」を上手に遠ざける、そんな面白い対策を試してみませんか?
LEDテープライトで「明るい結界」を作り出す!
LEDテープライトを使って家の周囲を囲むことで、ハクビシンを寄せ付けない「明るい結界」を作り出すことができます。この方法は、ハクビシンの光に弱い性質を利用した効果的な対策なんです。
「え?ただ明るくするだけでいいの?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果があるんです。
夜行性のハクビシンは、明るい場所を本能的に避ける傾向があります。
LEDテープライトの設置のポイントは以下の3つです:
- 家の周囲を隙間なく囲む
- 地面から30?50cm程度の高さに設置
- 動きセンサー付きのものを選ぶ
まるで、光の城壁を作るようなイメージです。
「ここは人間の領域だぞ」とハクビシンに主張しているようなものですね。
設置高さは、ハクビシンの目線に合わせるのがコツ。
地面から30?50cm程度の高さが最適です。
ちょうどハクビシンが這い上がろうとしたときに、目にぎらりと光が入る高さなんです。
動きセンサー付きのLEDテープライトを選ぶと、さらに効果的です。
突然の明かりの変化に、ハクビシンはびっくりして逃げ出してしまいます。
「うわっ!何だ何だ!」という感じでしょうか。
この方法の良いところは、見た目にも美しいこと。
夜の庭を幻想的に照らすLEDの光は、防犯効果も高めてくれます。
また、省電力なので電気代も心配ありません。
ただし、注意点もあります。
近隣への光害に配慮することと、野生動物の生態系への影響を考えることです。
明るすぎる光は、他の生き物にも影響を与える可能性があります。
LEDテープライトによる「明るい結界」、試してみると案外効果があって驚くかもしれません。
ハクビシンの習性を理解し、それを利用した賢い対策。
光で作る不思議な結界で、ハクビシンとの上手な付き合い方を見つけてみませんか?
動きと音で威嚇!「風車やピンウィール」の活用法
風車やピンウィールを庭に設置することで、ハクビシンを効果的に追い払うことができます。この方法は、動きと音でハクビシンを驚かせる、ちょっと変わった対策法なんです。
「え?子供のおもちゃみたいなもので効果があるの?」と思われるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
ハクビシンは新しい物や予測できない動きを警戒する習性があります。
風車やピンウィールの活用法のポイントは以下の3つです:
- ハクビシンの侵入経路に設置する
- キラキラと光る素材のものを選ぶ
- 複数の種類を組み合わせる
ハクビシンがよく通る場所、例えば庭の入り口や果樹の周り、家の壁際などに設置しましょう。
「ここは通れないぞ」とハクビシンに伝えるイメージです。
素材選びも大切です。
キラキラと光る反射素材のものを選ぶと、月明かりや街灯の光を反射して、より効果的です。
「キラッ」という予期せぬ光の反射に、ハクビシンはびっくりしてしまうんです。
また、複数の種類を組み合わせるのも効果的です。
風車、ピンウィール、風鈴など、動きや音の違う物を組み合わせることで、ハクビシンを更に混乱させることができます。
「カラカラ」「キーン」「カタカタ」と、様々な音や動きがハクビシンを警戒させるんです。
この方法の良いところは、見た目にも楽しいこと。
カラフルな風車やピンウィールは、庭を明るく彩ってくれます。
「わぁ、素敵な庭ね」なんて、近所の人に褒められるかもしれませんよ。
ただし、注意点もあります。
強風の日は倒れたり飛ばされたりする可能性があるので、しっかりと固定することが大切です。
また、音が気になる場合は、風鈴は控えめにするなどの配慮も必要です。
風車やピンウィールによるハクビシン対策、試してみると案外効果があって驚くかもしれません。
ハクビシンの警戒心を利用した、楽しい対策方法なんです。
「くるくる回る不思議な物体」で、ハクビシンとの新しい付き合い方を見つけてみませんか?
コーヒーかすの「強い匂い」でハクビシンを寄せ付けない!
コーヒーかすを庭にまくことで、ハクビシンを寄せ付けない環境を作ることができます。この方法は、コーヒーの強い匂いを利用した、エコでおしゃれな対策法なんです。
「えっ、コーヒーかすでハクビシン対策ができるの?」と驚かれるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
ハクビシンは嗅覚が非常に発達しており、強い匂いを嫌う傾向があります。
コーヒーかす活用のポイントは以下の3つです:
- 乾燥させてから使用する
- ハクビシンの侵入経路に重点的にまく
- 定期的に新しいものと交換する
湿ったままだとカビが生えてしまう可能性があります。
天日干しで十分乾燥させるのがコツです。
まき方も重要です。
ハクビシンがよく通る場所、例えば庭の入り口や果樹の周り、家の壁際などに重点的にまきましょう。
「ここは通れないぞ」とハクビシンに匂いでアピールするイメージです。
また、効果を持続させるためには定期的な交換が必要です。
雨で流されたり、匂いが薄くなったりするので、1週間に1回程度の頻度で新しいコーヒーかすと交換するのがおすすめです。
この方法の良いところは、環境にも優しいこと。
コーヒーかすは土壌改良にも役立つので、一石二鳥の効果があります。
「庭の植物も喜んでるかも」なんて想像すると、なんだか楽しくなりますよね。
ただし、注意点もあります。
コーヒーかすを厚くまきすぎると、植物の生育に悪影響を与える可能性があります。
薄くまんべんなくまくのがコツです。
また、ペットがいる家庭では、誤食に注意が必要です。
コーヒーかすによるハクビシン対策、試してみると案外効果があって驚くかもしれません。
ハクビシンの鋭い嗅覚を利用した、おしゃれな対策方法なんです。
「良い香りのする庭」で、ハクビシンとの新しい付き合い方を見つけてみませんか?